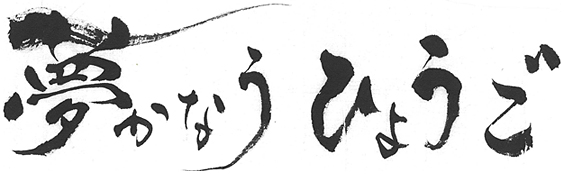暮らし【播磨町】兵庫に戻り魅力を再確認。団地住まいでコミュニティ創りに尽力

都市部と田舎の両方を体感できる魅力
播磨町
佐伯亮太さん
「明石に出てからアクティブになり、両親から〝性格が変わった〟と言われます(笑)」
都市部と田舎の両方を体感できる魅力
兵庫県豊岡市出身の佐伯亮太さんは中学校の卒業と同時に実家を離れ、明石市、山口県宇部市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市と県外を移り住んできました。
その後25歳で横浜から明石に戻り、現在は加古郡播磨町の築44年の団地の住人として、コミュニティファシリテーター(住民主体の地域づくりを担う人)の活動に力を入れています。
そんな佐伯さんは、県外各地を見てきたうえでの兵庫県の魅力を「自然の近さと暮らしやすさ」と説明します。

「子どもの頃は山の中を裸足で走り回っていました」と佐伯さん
「兵庫に帰ってきて感じたのは、都市部にいても自然が近く、田舎にいても都市部に比較的出やすい点です。まるで日本の縮図のように、どこに住んでも都市部と田舎の両方を体感できる暮らしやすさが魅力ですね。ちなみに友だちが加古川のことを〝とかいなか(都会と田舎を併せ持つ意)〟と言っていましたが、これは兵庫県全体に当てはまる表現だと思いますよ」
20歳で抱いた「まちづくり」への興味
神鍋高原スキー場で知られる豊岡市日高町で生まれ育った佐伯さん。中学卒業後は明石工業高等専門学校建築学科に進学し、寮生活を送ることになりました。
「地元は田舎で子どもが少なく、学校の選択肢も限られます。その田舎の進学校で中学の延長のような勉強をするより、もう少し違う学びに触れたくなって。一人っ子なので両親からは反対されましたが、僕の人生にとっては大きな決断のひとつだったと思います」
明石高専の建築学科に進学した佐伯さんは、クラスで常に成績優秀だったそうです。「ですが次第に点数を競い合うような勉強の仕方に疑問を感じ始め、先生に『もう勉強やめます』って宣言したんです(笑)」
以降は校外に活路を求め、DJ活動もしながら人脈を広げていきます。卒業後は就職するつもりでしたが、「せめて大学に……」との両親の希望で山口大学へ。そこで人生を左右する経験をすることになります。
「工学部のある宇部市は県の拠点都市のひとつですが、中心部ですら人が少なく閑散としていました。さらに同市の駅前再開発事業は学術的には高く評価されていたものの、実態はテナントビルの入居が埋まらず空家だらけ。20歳にして神鍋高原の農村、明石、地方都市の衰退という3つのケースを経験し、まちづくりに興味を持つようになったんです」
卒業後は横浜国立大学大学院に進んで建築を学ぶ一方、地元商店街のまちづくりプロジェクトに参加。ここで人生を左右する二度目の経験をしました。お世話になっていた青年部のみなさんに商店街活性化のアイデアをプレゼンしても、なかなか伝えられなかったのです。
「最先端の研究をしている自負がありましたが、自分の言葉が一ミリも通じない状況に衝撃を受けました。同時に、自分が学んでいることを両親に説明できないなと思い、視点を変えてもっと本格的にまちに関わりたいと考えるようになったんです」
いずれ母校の教員に――その目標達成と共に兵庫に
横浜にいるころから「いずれ兵庫に戻りたい」と考えていたという佐伯さん。理由は、「横浜で暮らす将来像を思い描けなかったから」でした。
「関東にいては両親に何かあってもすぐ帰れませんし、親族もいない土地で結婚して子育てして……と考えたとき、リアリティを持って自分の将来をイメージできなかったんです」
兵庫に帰るなら「東播磨か但馬」と考えていたところ、母校の明石高専が特命助教(リサーチ・アドミニストレーター)を公募していると知り、採用が決まりました。
「まだ大学院に在学中でしたが、『母校の教員になるのが目標』と教授に常々話していたこともあって、特命助教に採用されたと打ち明けて退学を決心しました。そして横浜から西明石に引っ越し、再び兵庫の地を踏むことになったわけです」
団地に住みながらコミュニティづくりを実践
念願の母校の教員となった佐伯さん。学生と地域をつなげるフィールドワークをしていた際、現在の住まいである播磨町の団地「コーポラスはりま西I棟」のオーナーと出会いました。

明るいクリーム色の外観に目を引くオシャレなロゴ
「オーナーご夫婦は団地の新たな価値を見出すべく、最上階の2戸を改装して共用のコミュニティスペースを設けていました。団地という緩やかなつながりのなか、住人同士が自然と交流できる場をつくりたい――そんなオーナーご夫婦の思いに共感し、入居させてもらうことになったんです」

最上階の共用スペース「hoccorito501」

2戸の入口をつないで共用スペースに
佐伯さんは大学院時代、「大勢でひとつの家に住むと何が起きるか?」というテーマで研究し、本にまとめていました。「僕が考えてきたコミュニティづくりを手さぐりで実践されている姿を見て、この団地でなら実現できるのではと考えたんです」と振り返ります。

「住人同士が交流するきっかけになれば」との思いで設けられた畑
入居後、佐伯さんはオーナーご夫婦とともに、様々な仕掛けをしていきます。
「ご高齢の住人でも気軽に立ち寄れるよう1階の1室を改装してコミュニティスペースをつくったり、イベントを定期開催したり。さらにピザ窯を手づくりし、ピザパーティをするようにもなりました。そうやって住人を主体としたコミュニティを少しずつかたちにしていき、住人同士や地域住民との交流が深まっていきました」

明石高専の学生が中心となり造り上げたピザ窯
移住希望者のニーズに応える情報発信を
現在は明石高専の特命助教は退任した一方、一般財団法人明石コミュニティ創造協会に所属して地域コミュニティの支援活動に従事するとともに、「合同会社Roof」を立ち上げて空き家活用などに力を入れています。
「移住フェアなどに参加して感じるのは、受入自治体の準備体制やPR活動に課題がある点です。地方に興味を持ってもらうためには、まずは移住希望者のニーズに応える情報発信が必要だと感じます」
そう指摘する佐伯さんは2017年、大阪大学大学院の工学研究科に進学しました。目的のひとつは、これまでの実践を体系的にまとめること。卒業後は地元のまちづくりに携わりたいと考えています。
「都会育ちと田舎育ちでは発見できるものが違うと感じます。田舎で育ったからこそ身についた感性があると思うんです。そんなアイデンティティを核とした学びの集大成を但馬に持ち帰り、いつか地元に還元していきたいですね」

「但馬出身の僕だからこそできる地元への恩返しがしたい」と佐伯さん
文・写真/高橋武男